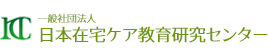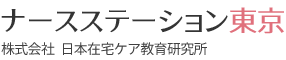今知りたい直近のアドバンス ケア プランニングと緩和ケア
~セミナー1:医療従事者とACP(2021.10.23)~
【Q1】透析患者さんへのACPのタイミングを教えて頂きたいです。
【A1】ライブ中継で回答済み
【Q2】テリー氏の治療中の医療費負担は、誰が行っていたのか?と思いました。米国の医療費負担額は非常に高い、というイメージがあるので
【A2】ライブ中継で回答済み
【Q3】コロラドは北米の中で、先進的な考え方のほうな州でしょうか。
日本は、宗教感も人種も大きくかけ離れておらず、保健・保険も整備されているほうだと思いますが、終末期の進む方向が難しいです。ご本人やご家族の希望より医師のタイプにより先が決まってしまうことがややみられる印象です。
テリーさんの希望はどうだったのか、自分の体験も含め心がざわつきました。
北米ならではの問題に対しての対策、実例を聞かせて頂き参考にさせて頂きたいです。
【A3】ライブ中継で回答済み
【Q4】訪問看護師です。在宅療養ではACPの話をするタイミングが難しいです。
【A4】ライブ中継で回答済み
【Q5】本人の意思を確認するとき、気を付けたいことは、援助者の考えが反映されないようにしておりますが、質問内容によってはその選択時からして援助者の思いなどが入りかねないのではと懸念があります。
【A5】ライブ中継で回答済み
【Q6】すみませんとぎれました、質問はあらかじめ決まった項目などがあるのでしょうか?
【A6】ライブ中継で回答済み
【Q7】ミーティングの途中で通信が途切れて講義が受けられなくなりました。録画で後日 視聴できませんか?
【A7】ライブ中継で回答済み
【Q8】たくさん質問してすみません。
ACPを実践したことがありません。前後のミーティングに参加したのみですが、時間を要するものだと認識しております。当社は訪問看護なので時間調整の壁があります。これは、複数回で聴取するものてすか?一度に聴取しますか?
時間と共に状況や症状、そして望みが変わっていくものだと思いますので、追いつくのだろうかと不安になりました。
【A8】その人の身体状況の理解度、家族や本人の受け入れ状況によりますが、40分から1時間はかかるつもりで準備しています。講演でも触れましたが、ACPはプロセスなどで、早い時期からどういうことについて考えなければならないか、しどうしていくことにより、手遅れにならないように心がけます。
【Q9】がんの終末期など、医学的には適応のない延命措置を患者さん本人が強く希望される場合、どのように対応されていますか?
【A9】ライブ中継で回答済み
【Q10】日本人の特性か文化か、利用者・家族ともに事前に人生会議をしてほしい、どのように自宅で過ごしたいか、万が一を見越して考えてほしいと伝えても「看護師は怖いことばかりを言う」となってしまったり、まだ大丈夫ですよなど事前準備ができないことが多いのですが、効果的な声かけはあるのでしょうか。
【A10】個人が望むケアを受けるには準備が必要なことを、十分に伝えあなたの希望を私たちがケア提供者として理解を深めるためのプロセスであることをしっかりと伝えることが大切です。話し合わないことによるリスクや残念な結果を避けるためにも大事なことだとわかってもらいように心がけます。年配の方々は医師がこれを選びなさいという哲学が普通だと思うことも多いので、「新しい考え方であなたの望むケアを提供し望まないケアを避けるためあなたの考えや思いを教えていただきたいす」というところから促してみてはいかがでしょうか。「最期に痛くて苦しいのは嫌だ」という人は多いですが、意思を伝えないとこのような結果も引き起こしかねないということも含めてお話ししてはいかがでしょうか。
【Q11】先ほど朝倉先生のお話にも少しありましたが、対象者が重度の認知症の場合、エンドオブライフについての本人の希望や思いを聞き取ることが難しい場合があるかと思います。ACPの概念がまだ浸透していない現在では、事前に明確な意思表示もない状況が多々あります。そういった場合、どうしても家族など本人以外の思いを優先せざるを得ない気がしますが、それを私たちはどのように考え、どうサポートしたらよいでしょうか。本人はどうしたかったのだろうか、といつもモヤモヤが残ります、、、
【A11】ライブ中継で回答済み
【Q12】意思や意向は書面などの記録に残すことが有効なのだと思うのですが、どの程度が有効と判断されるのでしょうか?あのときこういうことを言っていたという記憶では曖昧なので無効と判断されるのでしょうか?
【A12】ご本人が意思決定できない状況下においては、あの時こう言っていたという内容だけではなく、どのようなことがその人にとって大切だと思いますか、というところから模索していく方が、何を優先するのかを明らかにしやすいといえます。
【Q13】代理意思決定者が誰なのかを話し合う時に、代理決定者がプレッシャーに感じてしまうケースがありました。本人や、代理意思決定者に対して看護師として何かできることはありますか?
【A13】代理意思決定者がプレッシャーを感じるのは、間違った選択をしていないだろうかと戸惑うところからきています。特に安楽を目的としたケアへ移行した時、生命の長さを優先しなかったことに不安を覚える方も多いです。家族としてはいつまでも亡くならないでほしいという思いを乗り越えて、最期の時を穏やかに過ごすことを優先しています。その葛藤を理解して関わり、その判断が正しい判断であることを十分に伝えるよう心がけています。
【Q14】事前指示書を広めるにあたり、医療者含めACPの普及が重要だと考えます。文化の違いがある中、日本でも米国のように事前指示書は浸透可能であるとお考えですか。
【A14】私は、十分浸透可能だと思います。特に終活などのようにあらかじめ準備をしておきたいという意思を示す方が増えている中で、これを人生最期のひと時に広げていくこと、このような話をすることが普通なのだという風潮が必要です。まず私たち医療従事者がこれは常識的に常習的に行うものだという認識に変わる必要があるといえますが。
【Q15】生活保護で親族とも疎遠で何かあったら、生活保護の担当者に任せている。という、保護の方がいます。代理決定者になると思うのですが、本人の意思が反映されているのか、ジレンマを感じる時があります。親しい人がいない人の代理決定は、どうしていますか?
【A15】POLSTとMOSTの質問は全くと言ってよいほど同じです。タイトルが違うだけという感じです。チャプレンもいます、ご指摘のように、患者・家族だけでなく、スタッフの支えにもなっています。
【Q16】貴重で興味深い講演をありがとうございました。朝倉先生が来日されたら直接質問したいことがたくさんあります!
POLSTは検索してみられたのですが、MOSTは探せませんでした。コロラドオリジナルのMOSTがある、特徴的な部分はどこでしょうか。それは、なぜ必要とされオリジナルを作られたのか知りたかったです。そして一般的に、治療もそうですが、治療を受けることによりどのような日常が待っているのか、そのようなイメージもわからない方が多いと思います。朝倉先生は治療の先に待つ日常も説明され、サインを頂くのですか?先日、上智大学のチャプレンさんの講義を聴きました、朝倉先生の病院にはチャプレンさんはいらっしゃいますか?患者さまにとって、とても有り難い存在だと思いました。ターミナルの方の伴走は看護師も心が疲労します、救われたいと思う時があります。先生の体験された実際のお話も聴いてみたいです。
貴重な講義をありがとうございました。
【A16】タイトルが違うだけなのですが、POLSTは「生命維持に関する治療の医師の指示書」であるのに対し、MOSTは「治療の範囲に関する医療指示」というタイトルで、個人的にはMOSTの方が本人や家族の意思を反映するというニュアンスがより強いと思います。法的効力は同じです。 治療による負担も十分に話します。そのため、高齢の方で、がんだと分かっても抗がん剤治療などしないとわかっているばあい、生検などせず在宅ホスピスなどを選ぶ方もおおくおられます。病院にはチャプレンは、昼間は常勤で、24時間オンコールで対応します。患者家族のサポートに加えスタッフのサポートもおこないます。ちなみチャプレンは無宗教的な関わりをします。宗教に関わりなく、スピリチュアルケアを提供します。患者や家族が特に特定の神父などを希望した場合は、その人が病院を訪問することができます。
セミナー2:エンドオブライフケアにおける効果的なコミュニケーション技能(2021.11.20)
【Q1】もう数週間、数日で亡くなられるという状況で訪問を依頼されるケースも多くあり、短期間で利用者様、ご家族様との関係を築くことが難しいと感じています。そのような場合の関わり方についてアドバイスをいただきたいです。
【A1】短期間であっても達成できることはたくさんあります。実はあなたが思う以上にいろいろなことが達成されていると思います。あえて今後のそのような状況下でできることという点でお返事するのであれば、アセスメントをしっかりと行い、本人と家族の準備状態が整っているかを把握し、それに合わせて援助計画を立てること、そして第3回セミナーでお話しする全人的なアプローチで、穏やかな最期を迎えられるようにすると良いのではないでしょうか。
【Q2】早い段階からのアドバンスケアプランニングが必要なこと、プロセスであることは理解できているが、世間一般に理解しているかというと日本ではまだまだ理解していないと思う。私たちにできること、どのようなことからはじめていけばいいかなど教えてほしいです。
【A2】ACPで明らかにしたい項目、意思決定代理人や最期をどこでどのように過ごしたいというどのように希望を訪問時の記録の標準項目に追加するところから始めてはいかがですか?ACPはプロセスであり、状況や病状の変化により変わっていくことを踏まえ、どれくらい定期的に確認するのか(毎月など)も職場で決めておくと良いでしょう。
【Q3】ACPを職場で取り組み始めています。ACPのプロセスをどのような形式でどうやって管理されていますか。関わる人が共有しやすい方法などアドバイスいただければと思います。
【A3】Q2でも返答させていただきました、記録に残すと共に、調整会議やケアカンファレンスの標準項目に付け加えると良いと思います。私の職場でもICUの多職種ラウンドと言って平日毎日一人一人の患者さんについて話す場があります。この標準項目に意思決定代理人とケアゴールが入っていますので、身体状況と治療計画において緩和ケアチームも、患者さんの価値観などをシェアすることで貢献しています。
【Q4】自分の価値観でミスリードしているかもしれないという不安を常時持っています。 自分の仕事やプライベートでの経験がそれぞれ違うので個性が出るものだと思います。
ディブリーフィングは有効だと分かります。先生の施設で行われるディブリーフィングの頻度や、タイミングで効果的だった成功例を教えて下さい。また、自分の価値観、思考の癖が分かるようなフローやテストは存在しますか?
【A4】ディブリーフィングは、問題や困難な事例があった場合、できるだけ早く行うことが好ましいです。ディブリーフィングにはどのような立場の人も職種に関係なく参加できる環境が良いです。早いに越したことはありませんが、数日から1-2週間以内が良いでしょう。自分の価値観についてセミナーでは自分の事前指示書を書くというお返事をさせていただきました。それに加え、御自身の家族に事前指示書を作成していただき、その内容をシェアしてもらった時どのような気持ちかを自分自身について探究すると自分の傾向とともに家族としての想いを認識できる機会になります。
【Q5】否認が強く、自分の病状を受け止められない患者さんの場合、病状説明を繰り返すことは侵襲的になることもあると思いますが、どのように対応しておられますか?
【A5】否認は難しい問題です。本人が自覚している症状とリンクさせながら理解を促しますが、否認は感情反応であり、知識とは少し別のところにあります。知識だけでなく感情に対する働きかけが必要です。否認している感情は悪いことという捉え方にならないよう気をつけ、思いやりのある態度は必須です。最善の努力は常に行いますが、残念ながら否認が克服できずに亡くなる方も居るということも私たちは、受け入れなくてはなりません。
【Q6】ご本人や同居のご家族とは、ご自宅での看取りに向けてよい関係を築くことができ、しっかりと教育指導もできていたとしても看取りの直前にやってこられた微妙な関係のご親族(同居されていないごきょうだいや叔父叔母・甥姪あたりの方々)が、強く主張されて、救急車を呼んでしまったりして救急搬送されてしまう等、最期の時がご本人の望まない形で終わってしまった事例が少なからずありました。訪問看護師は事後に知らされることが多く、愕然とするしかないことも多々あるのですがこのような事例は米国ではないのでしょうか?日本の国民性や地域性(地方在住のため)によるものでしょうか?このようなご親族の心情は、先生のご講義のなかで説明のあった「家族の持つ恐れ」で理解はできますが具体的にこのような事態を避けるための、効果的な手法やアドバイスはございますでしょうか?ご家族には、看取り教育の中で「できる限りのご親族にも共有していただくように」とお伝えはしていますが突然やってきていろいろなぎ倒して去っていく嵐のような存在に思えて、なすすべが見当たりません…
【A6】おそらく最善の結果に向けてとても努力なさっていることと思います。その中でご本人の望まない最期は辛いですね。親密な家族とご本人の意思疎通を促す上で、ご本人や家族に他の家族とのコミュニケーションが取れているのか、また私の方から電話などでお話ししても良い旨をオファーするようにしています。またはご本人ご家族が他の家族と話す際どのように伝えるのか、どのような言葉を使うとよいのかなど教育を行うのも良いです。質問5の場合もそうですが、最善を尽くしますが、残念な結末はケアチームメンバーの感情を大きく傷つけます。ディブリーフィングなどを活用して感情をシェアできる場そしてさ支え合う場が必要ですね。
【Q7】講義して頂いている内容は普段の医療現場でもスタっフなどに継続的に教育していく重要な内容だと思います。テクニカルなものだけではなく相手の価値観を知ろうとする向き合う姿勢、コミュニケーションスキル」をシステマチックに教育に導入していくためにどの様な工夫が出来るでしょうか?
【A7】ご指摘のように、講義などで知識をつけるだけでは、コミュニケーションスキルの向上には限界があります。ロールプレイは苦手な人も多いですが、それは体験型のスキル習得方法だからです。ですから私はロールプレイはよく行っています。また、トレーニングの中で、訪問前にどのようなことを話すかある程度準備していくという方法もとっています。対象者や家族の反応は様々で、柔軟性が必要ですので、いくつかの想定される反応に対する対応を訪問前に言語化するという準備も良いでしょう。
【Q8】アメリカでのこの様な教育システムは何かありますか
【A8】どのような、言葉かけや質問の方法などを提案するVitalTalk® など近年活用されています。私もスタッフ教育などで活用しています。
【Q9】ご家族の希望などで本人に未告知の終末期の患者さんに対してはどのようにアプローチしていけば良いのか悩みます。何か良い方法はありますでしょうか。
【A9】私は医療情報を整理するところから始めて、その医療情報をもとに予期される今後について、お話ししていきます。ご本人がエンドオブライフについての認識が深まると、どれほど時間があるのかなど、ご本人から聞かれることが多いです。お話をする際、ご家族に同席したいか伺います。ほとんどの方は同席して一緒に支えたいとおっしゃいます。
【Q10】ディブリーフィングを行なう上でファシリテーター担当になるスタッフが気を付けなければいけないことはありますか。話の進め方で自分が看護師としての視点でいることが多くミスリードをしてしまっているのでは?と感じることがあります。
【A10】誰かを咎め始める発言をしないなど、あらかじめ注事項を確認して始めると良いです。それぞれの感情に焦点をおくことが大切です。この様に思わなくてはならないと肯定的な感情であっても誘導的にならない様に、気をつけると良いと思います。ネガティヴな感情であっても、それを否定しないよう気をつけると良いです。
【Q11】財産を多く持つ(お金で解決してきた)方のほうが自分の死を受け入れることに抵抗が強いように感じます。朝倉先生もそのように感じたことはありますか?また、そのような時にはどのように対応をされましたか?
【A11】特に財産が多い方という印象はありませんが、ご指摘の点はこれまでのコーピングスキルとしてのお金では、死を避けるということに適応されないという例ではないでしょうか。今まで経験したことのない、自分の力では変えることができない迫りつつある死に対して、新しいコーピングを促進する取り組みが必要となります。ライフレビューなどでの、これまで達成できたことを言語化できるよう支援し、残った時間でさらに何を達成できるかを話し合うという関わりを持つよう心がけています。